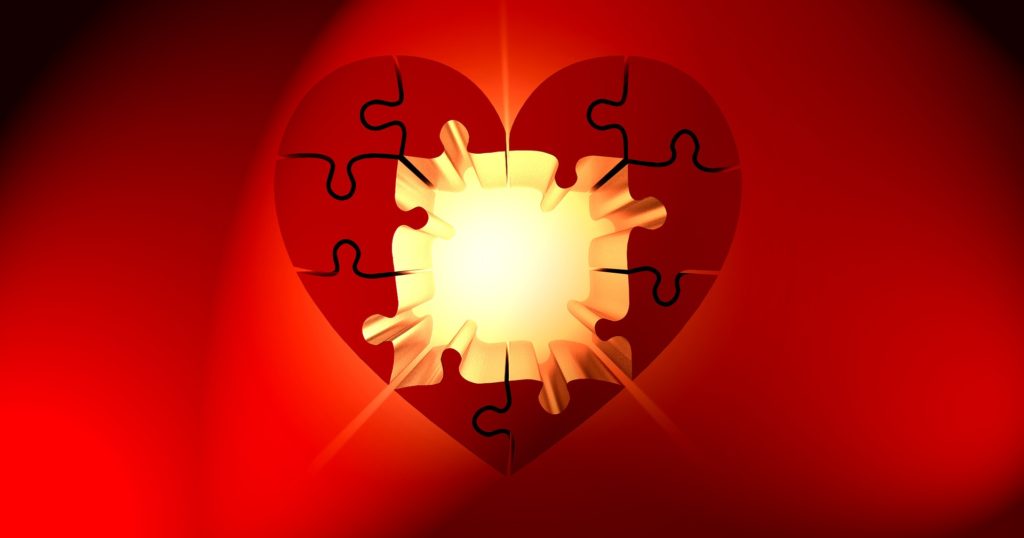「会議で発言できない・発言が苦手」そんな悩みへのタイプ別対処法【会議の悩み】

この記事はプロモーションが含まれます。
- 会議で発言できなくて困っている
- 会議で発言を求められたときにうまく発言できない
- 会議で自分から発言しないと怒られる
このような疑問にお答えします。
本記事の内容
- 会議で発言できない原因をタイプ別に考えます
- 会議で発言できない原因への対処法をタイプ別に解説します
「会議で発言しない人=いる意味がない」みたいなことを言ってくる人っていませんか?
これって、「誰が何のためにその人を呼んだのか」にもよると思うんですよね。
なので、呼んだ人が会議の目的や呼んだ意味をきちんと本人に伝えているかどうかも大切なはずなんですね。
なんか知らないけど呼ばれた会議で「自分から何かしゃべれ」だけだとつらいじゃないですか。
とはいえ、会社の風土や上司の考えによる部分も大きいと思うのですね。
そこで、今回は『会議で発言できないことへの対処法』について解説していきたいと思います。
会議で発言できない原因
会議で発言できない、発言しにくい、発言が苦手、緊張する…
このように思う原因は大まかに3タイプあるかなと思います。
- 心理的なもの
- 環境的なもの
- 理解的なもの
この3つなのですね。
それでは順に解説してきます。
あなた自身であったり、同僚や部下の方がどのタイプにあたるかイメージしながら読み進めてもらえればと思います。
発言できない原因① 心理的なもの
自分自身の感じ方に原因があるパターンです。
主に
- 見当違いなことを言ったらどうしよう…
- 自分の発言が批判されたらどうしよう…
- 何か言いこといわなきゃ…
こんな感じのことを思ってしまうことで、発言を躊躇してしまう場合なのですね。
これは『メンタルブロック』とも言います。
それでは1つずつ見ていきましょう。
見当違いなことを言うことへの不安
発言したはいいものの、ぜんぜん見当違いなことを言ってしまって
周りから「は? 何言ってんの?」って言われるのはある種の恐怖なのですね。
とくに自分より役職が上の人が多い会議だといたたまれません。
あげく「誰だよ、こんなやつ呼んだのは?」とか言われたりと、不安は膨らむばかりです。
対処法:見当違いかどうかは言ってみないとわからない
いきなり精神論じゃんって思われそうですが、「見当違いかも…」ってことは「見当違いじゃない」ってこともあるはずなのですね。
そもそも、確実に「見当違いじゃない発言をする」というのは不可能です。僕も「あれ? 何か違った?」ってことはありますし。
こればっかりは言ってみるまでわからないのです。
なのでこういうのはどうでしょう?
「もしかしたら見当違いかもしれないんですけど…」
と枕詞をつけて発言する。
事前期待を自分で下げるという戦法です。
保険をかけておくともいいます。
それでも冷たい反応をされたら
「そもそも、こんな会議に呼ぶなよ」って逆切れしましょう。心の中で。
自分の発言が否定されることへの不安
発言したはいいものの、「それは違うだろ」って否定されたり、反論されたりするのもある種の恐怖なのですね。
別にそこまで言わなくてもいいじゃんっていうくらい攻撃してくる論破マンみたいな人もいたりしますからね。
対処法:肯定されるか否定されるかは言ってみないとわからない
そうですね。さっきと同じじゃんって思いましたよね。
しかしですね、誰が肯定派で誰が否定派に回るかなんてことは、言ってみないとわからないわけなのですよ。
仮に否定されてしまったとしたら、別に説得とかする必要はないので「あ、すみません」で終わらせてしまえばいいのですね。
「たまたま意に沿わなかっただけ」と受け流しましょう。
そういうことはよくありますので。
ちなみに、論破マンは何を言っても攻撃してきますから「そういう生き物」と思ってください。
相手を攻撃することでしか自分を表現できない悲しい生き物なのですね。
何かいい発言をしないといけないという不安
見当違いでもなく否定もされないような発言をしなければ…という不安は
的を得て肯定されるような発言をしなければいけないというプレッシャーへ変わるのですね。
対処法:誰も期待してないから大丈夫
身もふたもないかもしれませんが、よほどの有識者のポジションにいる人でないかぎり、発言に注目されることはないのですね。
なので変に気負わずに発言してみることをおすすめします。
もしかしたら
「もうちょっと気の利いたこと言えよ」って言われるかもしれません。
または、とくに取り上げられもせずスルーされるかもしれません。
ですが、あなたの意見がきっかけで妙案が生まれることだってあるのですね。
発言できない原因② 環境的なもの
ちょっと心理的に似てるかもですが、こっちは自分の受け取り方ではなく環境のほうに原因があるパターンになります。
この3つで考えています。
- 発言したいのに発言する隙がない
- 特定の人ばかりで話していて参加しづらい
- すごい発言しづらい雰囲気
それでは1つずつ見ていきましょう。
話が途切れないので発言する隙がない
いざ発言しようと思っても、どんな阿吽の呼吸よ? ってくらいに話が途切れず、まったく発言する隙がないことってありませんか? それのことです。
進行役が機能していない会議でありがちです。
そのなかで「何か発言しろ」っていうのはなかなか難しいのですね。
対処法:そっと手を挙げてみる
途切れない会話に割って入るというのは難度が高いです。
タイミングと声の大きさも重要になります。
小さな声だと一瞬でかき消されてしまいます。
そこで、そっと手を挙げてみる…というのはどうでしょう?
「あのぅ、ちょっとよろしいでしょうか」的な雰囲気で
話している人たちの視界に入るように、そっと手を挙げます。
そうすると、たいていの場合は、「お、どうした?」と気に留めてくれて話をふってくれたりするのですね。
もしガン無視されてしまったら、そっと手を引っ込めて、次のチャンスを待ちましょう。
特定の人ばかりが話していて参加しづらい
発言する隙がないのと似ているかもですが、発言する人が決まっていて、他の人がなんとなく発言しにくい雰囲気の場合です。
そんななかで「何か発言しろ」というのは「そりゃないぜ」ってかんじですね。
対処法:あえて黙っている
戦略的沈黙です。
考えてもみてください。
特定の人ばかりで議論している会議というのは、基本的に外野の意見は聞かないものですし、発言しない人たちもそんなにやる気はないはずです。
これは会議のあり方そのものに問題があるのですね。
なので、そんななかあえてあなたが特攻をかける理由はないと思います。
「発言しないと降格」みたいなハードミッションを課せられていないかぎりは、黙っているでよいと思うのですね。
すごい発言しづらい雰囲気
なんか偉い人が難しい顔していたり、しかめっ面して腕組みしてたり、なんかすごい発言しづらい雰囲気の会議ってありませんか? それのことです。
他の人の参加者も発言しないなかで「何か発言しろ」っていうのはなかなかのハードモードなのですね。
対処法①:おとなしくしている
これも戦略的沈黙でいきましょう。
へんな話、こんななかで「何を発言しろっちゅうねん」ってことなのですね。
もし上司に何か言われたら「いや、無理ですよ」って正直にいいましょう。
上司とのコミュニケーションも大切なのですね。
対処法②:上司に発言の機会をつくってもらう
上司とのコミュニケーションという点で、会議中に自分に意見を求める機会を作ってもらうように事前にお願いしておくという手もあります。
「自分から発言しづらい雰囲気なので、話を振ってもらってよいですか」みたいなかんじです。
「ダメだ」と言われたら、あきらめましょう。
発言できない原因③ 理解的なもの
会議で発言するということは、会議の目的、議題や議論の内容を理解している必要があります。
理解が浅いと、何を発言していいかもわからないのですね。
心理的なものは、気の持ちようでもあるので自分に左右されます。
環境的なものは、自分で変えられないものもあるので他人に左右されます。
ですが、この理解的なものは、自分の仕事のしかたを変えることで対処が可能になります。
ここではこの3つで考えています。
- 専門用語やヨコ文字の意味がわからない
- 何について議論しているのかわからない
- 何を言えばいいのかわからない
それでは1つずつ見ていきましょう。
専門用語やヨコ文字の意味がわからない
「それ日本語で言えばよくない?」ってものと、その界隈での専門用語が入り乱れて会話されたりします。
コンセンサス(合意)、フィックス(確定)、バジェット(予算)とか、日本語で言えばいいじゃんってものもあれば
コンバージョン、トランザクション、アジャイル、モジュールといった専門用語的なものもあり、主にマーケティングやシステム開発がテーマだと専門用語での会話が多いように思います。
言っている方も本当に意味がわかって使ってるのか疑問だったりしますが、さも常識のように使ってくるのはやめてほしいところです。
対処法①:思い切って質問してみる
「すみません、アジャイルってなんですか?」って思い切って質問してみます。
そんなのも知らないのって反応をされるかもしれませんが、あなたの他にも実はわかっていない人がいるかもしれないのですね。というか必ずいます。
誰もがその場で確認するということはしづらかったりします。
ですが、あなたの質問によって、参加者の認識が揃う結果になるかもしれないのですね。
対処法②:メモしておいて後で調べる
その場での質問はどうしてもしづらい。かといって、その場ですぐに調べるのも難しい。
そんな方には、メモをしておいて後で調べることをおすすめします。
1戦目はあえて負けて、2戦目から発言できるように準備をするという戦法なのですね。
上司になにか言われたら「すみません、次は行けます」と言っておきましょう。
何について議論しているのかわからない
話についていけていないというパターンです。
よほど関係のない会議に呼ばれたのでなければ、なるべく話についていき議論に参加できるようにしたいものなのですね。
話についていけない理由は主に2つかなと思います。
- ① 議論の内容がとっちらかっていて何について話しているのかわからない
- ② 議題への理解が足りていないため議論の内容が理解できない
それぞれ対処法のなかで説明したいと思います。
対処法①:思い切って質問してみる
【①議論の内容がとっちらかっていて何について話しているのかわからない】ときは、思い切って質問してみます。
議論をしていると論点がずれることはよくあるのですね。
たとえば、予算の話をしていたかと思えば、いつのまにかスケジュールの話になっていたり、かと思えば、人員の話をしていたりします。
このように論点が錯綜していることで「何について議論しているのかわからない=話についていけない」となっているのであれば、これは質問してみるしかないのですね。
他の人もわかっていない可能性もありますし、もしかしたら議論してる人たちも最初の論点を見失っているかもしれません。
「あのう、自分の理解不足ですみません。いま〇〇についての議論ということであっていますか?」
みたいなかんじで、おそるおそるへりくだって質問してみましょう。
言い方を間違うと議論している人たちのプライドを傷つけて面倒くさいことになることもありますので、下手にでるのがコツなのですね。
対処法②:予習しておく
【②議題への理解が足りていないため議論の内容が理解できない】ときは、事前準備として予習をしておくことをおすすめします。
「話についていけない」とわかった時点では遅いのですが、「そうならないようにするために」という意味での対処法です。
できれば事前にしておいたほうがいいことは主に次の2つです。
- 議題の内容を確認しておく
- 会議資料を入手して確認しておく
会議に関する情報を事前に確認して、わからないことがあれば上司などに聞いておくとよいのですね。
何を言えばいいのかわからない
議論の内容は理解できているけど、何を言えばいいのかわからない。
これは「思っていることはあるけど言えない」ということではなく、そもそも「言うことが思いつかない」というパターンなのですね。
「言うことが思いつかない」のであれば「思いつく」ようにならないとです。
「思いつく」ためには、会議資料や議論の見方である『観点』が必要になります。
対処法:上司や先輩に観点を教えてもらう
これも会議のときに「何を言えばいいのかわからない」だと手遅れなので、「そうならないようにするために」という意味での対処法になります。
素直に上司や先輩に「観点」について教えてもらうのが早いと思うのですね。
「たとえば上司や先輩だったらどういう観点でみているか」を教えてもらって、自分の観点を鍛えていきましょう。
まとめ:打席に立ってバットを振り続けましょう
- 発言できない理由は、心理的・環境的・理解的の3種類
- 心理的なものは、自分の気の持ちようになる
- 環境的なものは、他人に左右されるので、ときには上司の力も借りる
- 理解的なものは、自分の仕事のしかたを変える
上記のとおりです。
自分より職位が上の人たちばかりの会議で発言するのはとても緊張します。
周りの視線や表情、反応はとても気になるのですね。
準備を十分に整える
最初は勇気
場数を踏むことで度胸をつけていく
発言を繰り返すことで観点を鍛えていく
とにかく「打席に立って、見送らずにバットを振っていく」ことが最大のコツになります。
そもそも発言に「合っている・間違っている」はありません。
偉い人たちのリアクションは非常に気になるところですが、あなたの発言によって、議論が活発になったり、重要な論点が見つかったり、他の参加者の理解を助けたりと、よりよい会議になることもあるのですね。
まずは比較的発言しやすいと思う会議から実践してみて、場数を踏みながら徐々に慣れていくというのはどうでしょうか。
ではでは
お疲れさまでした。

お呼びでない感がつよいわー