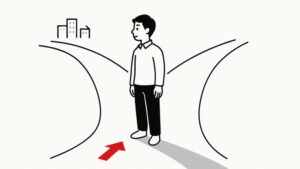【上司との会話がかみ合わない原因】“事実”と“解釈”の違いを知るだけでロジカルに話せるようになる
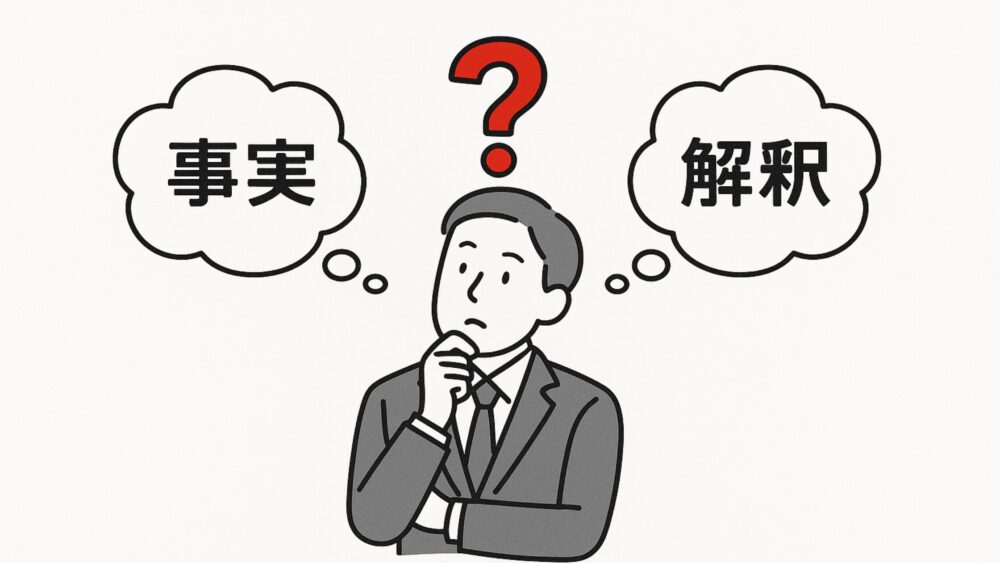
「それ、本当に“事実”ですか?」
——解釈と混同した瞬間、あなたの仕事はズレ始める。
会議のあと、こんなモヤモヤを抱えたことはありませんか?
「あれ?なんで話が噛み合わないんだろう」
「言ってないことを“そういう意味だったんですね”と決めつけられた」
「上司の指摘が、ただの“感想”にしか聞こえない…」
実はその違和感、すべて「事実」と「解釈」がごちゃまぜになっていることが原因かもしれません。
ビジネスの現場では、驚くほど多くの人が“事実のように話された解釈”に振り回されています。あなたの上司も、もしかしたらそのひとりかもしれません。
でも安心してください。
この“混乱”には明確な対処法があります。
本記事では、以下の3点をわかりやすく解説します。
- そもそも「事実」と「解釈」は何が違うのか?
- 混同しがちな会話の中で、どうやって見分けるのか?
- なぜこの区別が、仕事の質や人間関係を左右するのか?
読み終わる頃には、あなたは「見える景色」が変わっているはずです。
そして、言葉の使い方ひとつで、伝わる・伝わらないの差がどれほど大きいかに気づくことになるでしょう。
事実と解釈の違い——なぜ分けて考えるべきなのか?
あなたは、こんなやりとりを経験したことはありませんか?
「ちゃんと報告したはずなのに、伝わっていなかった」
「言ってないことまで“そういう意味でしょ?”と決めつけられた」
もしかすると、その混乱の原因は——
「事実」と「解釈」がごちゃまぜになっていたからかもしれません。
ここでは、ビジネスでも日常でも役立つ「事実と解釈の見分け方」を、具体例とともに解説していきます。
そもそも「事実」とは?
まずは基本から押さえておきましょう。
事実(じじつ)とは?
実際に起こったこと、現実に存在すること。
たとえば:
- 2019年5月1日、日本の元号が「令和」に変わった
- 東京都庁は新宿区にある
こうした内容は、「誰が見ても変わらない」「確認すれば一致する」もの。
つまり、事実は“客観的”であるというのがポイントです。
では「解釈」とは?
一方で、こちらはどうでしょう?
解釈(かいしゃく)とは?
物事や人の言動などについて、自分なりに考え、理解すること。
たとえば:
- セブンイレブンの店舗数は多い
- 今年の冬は暖かい
- このスマホは高い
…といった表現。
どれも「何と比べて?」という基準が人によって違うものばかりですね。
つまり、解釈は“主観的”で、人によって変わるというのが大きな特徴です。
【例で納得】事実と解釈のちがい
ここからは、もっとイメージしやすい具体例で比較してみましょう。
■ 例①:気温について
- 事実:今日は気温が35度ある
- 解釈:今日は暑い
→「35度」は気象データとしての事実。
→「暑い」は人によって感じ方が違う主観。
■ 例②:商品の価格について
- 事実:このスマホは10万円する
- 解釈:このスマホは高い
→「10万円」という価格は誰が見ても変わらない事実。
→「高いか安いか」は、その人の収入や価値観で変わる解釈。
まとめ|“客観”か“主観”かで見分けよう
覚えておきたいのはこのポイント:
| 区別軸 | 内容 |
|---|---|
| 事実 | 客観的な情報。誰が見ても変わらない。検証できる。 |
| 解釈 | 主観的な感想。人によって異なる。感情や判断が含まれる。 |
「今、自分が口にしているのは“事実”なのか、それとも“解釈”なのか?」
この問いを意識するだけで、あなたの伝え方・受け取り方は一段とクリアになり、仕事の精度もグッと上がるようになります。
事実と解釈の区別がついていないことは案外多い
「事実と解釈の違い? そりゃあ、簡単でしょ」
そう思ったあなた。……実は、頭ではわかっていても、会話の中では無意識に混同していることがとても多いんです。
特にビジネスシーンでは、“言ったつもり・伝わったつもり”のミスコミュニケーションが、あとから大きな手戻りや誤解を生んでしまうことも。
その典型的なパターンが、以下の2つです。
- 事実を聞かれているのに、解釈で答えてしまう
- お互いにあいまいな言葉だけで会話してしまう
それぞれ具体例を見ながら、「なぜ非効率になるのか?」を一緒に考えてみましょう。
事実を聞かれているのに、解釈で答えてしまう
ある日、こんなやりとりがあったとします。
上司:契約、とれた?
部下:説明はかなりうまくいったと思います。
上司:え?じゃあ契約とれたの?
部下:いえ、まだです…。
上司:じゃあ、何が足りなかったの?
部下:予算に納得いってない感じでした。
上司:具体的に、どの部分?
部下:うーん、全体的に…ですかね。
上司:他の部分は問題なかったってこと?
部下:たぶん大丈夫だと思います。
一見、ちゃんとやりとりしているように見えますが、実は上司が求めている“事実”に、部下がすべて“解釈”で答えているのが問題です。
このやりとりで起きていること
| 上司の質問 | 求めているのは… | 部下の返答 | 実はこれ… |
|---|---|---|---|
| 契約とれた? | 事実(Yes/No) | 説明はうまくいった | 解釈 |
| 条件は何? | 事実(具体要因) | 予算に納得いってない感じ | 解釈 |
| 予算の何が? | 事実(詳細) | 全体的に納得してない | 解釈 |
| 他に問題は? | 事実(有無) | たぶん大丈夫 | 解釈 |
このように、事実と解釈がごちゃまぜになると、上司は状況を正確に把握できず、的確な判断も指示もできません。
結果、どうなるかというと——
- 要点がぼやけて次の一手が見えなくなる
- 確認作業が増えて二度手間・やり直し
- 思い込みで進んでズレた対応・トラブルの原因に
こうした“伝わっているようで伝わっていない”やりとりは、あなたの周りにも案外多いのではないでしょうか?
あいまいな言葉で会話している
もうひとつのよくあるパターンがこちら。
「それ、定義があいまいすぎて伝わらない」問題です。
Aさん:うちの部の課題って何がある?
Bさん:Eさんは営業力が足りないですよね。
Cさん:F課長のマネジメント力にも課題があると思います。
Bさん:G課長は当事者意識あるけど、F課長はないように見えます。
Aさん:じゃあ、Eさんには営業力をつけてもらおう。F課長にはマネジメント力と当事者意識を…。
ここでの問題は、“営業力”や“マネジメント力”、“当事者意識”といった言葉が、誰にとっても定義がバラバラなこと。
その結果、起きるのはこんな現象です。
- 「営業力」って何を指してる? → 人によって違う
- 「当事者意識がない」って何をもって? → 見え方の問題?
- 「マネジメント力」って成果?人望?プロセス? → 解釈の解釈になってしまう
つまり、共通認識のない“解釈同士”で会話しても、具体的な改善にはつながらないのです。
どうすればいいか?|言葉を定義すればOK
あいまいな言葉は、「どんな意味で使っているのか?」を定義してから使うのが鉄則。
たとえば、「営業力」を定義するなら
- 清潔感のある身だしなみ
- 商品理解力
- 提案書の作成力
- 訪問件数
- 信頼関係を築くトーク力
このように「要素分解」すれば、
何が足りなくて、何を伸ばせばいいかが“誰にとっても明確”になります。
まとめ:事実と解釈を分けるだけで、仕事は驚くほどスムーズになる
「事実」と「解釈」がごちゃごちゃのまま進むと、
手戻り・誤解・非効率・トラブルがどんどん積み重なります。
でも、逆に言えば——
ほんの少し、「今のは事実?解釈?」と自分に問いかけるだけで、会話の質が劇的に変わるのです。
次章では、こうした区別を“日常業務に活かす”ためのコツを解説していきます。
「伝え方」「聞き方」「書き方」それぞれで、どう実践していけばいいのか?
実用的なヒントを具体的にご紹介していきます。
事実と解釈を区別するコツ
「事実は客観」、「解釈は主観」——
ここまで読んでくださったあなたなら、もう違いの基本は理解されていると思います。
でも、実際の会話の中では、どちらなのか迷う瞬間もあるはずです。
そこで最後に、「それって事実?それとも解釈?」を一瞬で見分けるコツをお伝えします。
客観=「YES or NO」で答えられる/数字で示せる
まずは“事実=客観”の判断基準から。
YES/NOで答えられるか?
- 「契約は取れましたか?」→ YES or NO
- 「この資料は提出済みですか?」→ YES or NO
→ これらは誰が答えても同じになる質問です。
にもかかわらず、返答が
- 「けっこう手応えはありました」
- 「たぶん大丈夫だと思います」
…となると、それはすでに“主観”=解釈に入ってしまっている、というわけですね。
数字で示せるか?
数字は最強の客観情報です。
| 主観の言い方 | 客観への変換例 |
|---|---|
| かなり時間がかかる | 完了までに7営業日かかる |
| ほとんどの人が反対している | 回答者の75%が反対した |
| 売上が上がっている | 先月比+12% |
「感覚」ではなく「データ」で語ることが、客観性の鍵になります。
主観=抽象的な言葉/語尾に「〜と思う」「〜な気がする」
一方で、“解釈=主観”の特徴はどうかというと…
抽象的で、定義があいまい
- 主体性がない
- リスクがある
- やる気を感じない
- 営業力が足りない
こうした言葉は、「何をもってそう言えるのか?」が人によって違います。つまり、主観のかたまりなんです。
語尾に“思う”“感じる”“見える”がつく
- 「たぶんうまくいくと思う」
- 「納得してないように見えた」
- 「やる気がない気がする」
これらはすべて、推測・印象・憶測の域を出ません。
もちろん、主観がすべて悪いわけではありません。
ただ、それを“事実として伝えてしまう”ことが問題になるのです。
明日からできる!事実・解釈チェックリスト
文章でも会話でも、「それ、事実?解釈?」をチェックしたいときはこの2つを思い出してください:
| チェック項目 | YESなら… | NOなら… |
|---|---|---|
| YES/NOで答えられる? | 客観(事実) | 主観(解釈)かも |
| 数字・固有名詞で説明できる? | 客観(事実) | 抽象的すぎるかも |
まとめ|言葉を整えると、思考も仕事も整う
「なんとなく伝わってる気がする」
「ちゃんと説明したつもりだったのに…」
そんなミスコミュニケーションのほとんどは、事実と解釈の混同から生まれています。
けれど、それをほんの少し意識するだけで、驚くほど会話はスムーズに、仕事の精度も上がるのです。
“伝える”はスキル。“伝わる”はテクニック。
その第一歩が、「事実と解釈を分けること」です。
次の会議、上司との報告、メール文。
どれかひとつでいいので、まずは試してみてください。
きっと、相手の反応が変わるはずです。
ルールを決めても、現場では機能しない
「よし、これからは会話のときに“事実と解釈を明言する”ってルールにしよう!」
…そう思った方、ちょっと待ってください。
ビジネスの議論は、課題を見つけ、解決へと導くためのもの。
しかし、その場でいきなり「はい、これは事実です」「今のは解釈です」と明言しながら話すのは……現実にはかなり難しいのが本音です。
正直に言えば、僕自身も完璧にできていません。
解釈はどうしても会話の中に入り込んでしまうものです。
そして何より、ルールを敷いても——
- 守れない人が出てくる(というか大多数がそう)
- 自分自身もずっと意識するのはしんどい
- うまくいかなかったときに“自分で作ったルール”が首を絞める
こんな状態になってしまっては本末転倒ですよね。
だからこそ、「ルールで縛る」よりも「自分で見極められる力をつける」方が、ずっと実践的で現実的なんです。
まとめ|相手に期待せず、“自分の受け取り方”を変えよう
最後にもう一度、この記事の要点を整理しておきましょう。
事実と解釈を見分ける3つのポイント
- 事実は「誰が見ても変わらない」客観情報
→ YES/NOで答えられる、数字・日付・固有名詞などで表現できる内容。 - 解釈は「人によって異なる」主観的な意見
→ 抽象的な言葉や「〜と思う」「〜な気がする」などが目印。 - 迷ったら“数字で語れるかどうか”を判断軸に
→ 感覚ではなくデータで語れるか?を意識すると、精度が上がります。
なぜ“解釈まみれの会話”は危険なのか?
- 議論がかみ合わない
- 論点があいまいになって課題が解決しない
- 誤解・手戻り・トラブルにつながる
- 結果、チーム全体が“非効率スパイラル”に陥る
→「なんかずっと会議してるけど、何も決まらない」状態は、たいてい解釈同士の応酬が原因です。
全員で「事実ベース」を徹底するのは難しい
「今後は全員、事実と解釈を区別して話しましょう!」というルールを設けたところで——
- 多くの人は無意識に主観で話してしまう
- 自分自身もずっと完璧には守れない
- 守られないルールは逆にフラストレーションの原因になる
→ 結果、ルールは形骸化してしまいます。だからこそ、自分自身が“受け手としてのスキル”を高める方が確実なのです。
自分の受け取り方を変えれば、仕事はラクになる
- 相手の発言を「これは事実かな?解釈かな?」と分類する習慣を持つ
- 解釈のまま話す人にイライラするのではなく、自分の中で整理して受け取る
- あいまいな言葉は「どういう意味で使ってる?」と確認することで認識を合わせる
→ 相手に“変化”を求めるのではなく、自分の思考の解像度を上げることが、最大の武器になります。
「それ、事実ですか?」は禁句です(笑)
上司や先輩が
「もっと主体性持ってくれよ」
「あの案件はなんか不安だよね」
こんなことを言ってきたら——
このとき、あなたがいくら論理派でも、
「それは事実ですか?それとも解釈ですか?」
なんて返してしまうと、あなたのキャリアに“不要な波紋”が広がる可能性大です。
→ だからこそ、“自分の中で整理する”だけでOK。相手を変えようとしなくていいのです。
今日から実践できる「聞き方の習慣」
- 心の中で「それは事実?解釈?」と問いながら聞く
- 解釈っぽい発言は、事実に分解してメモをとる
- 自分が話すときは「数字」「事実ベース」を意識する
これだけで、会話の質と理解力がぐっと上がります。
最後にひと言
伝え方にこだわるより、受け取り方を変える方がずっと簡単。
相手が変わらなくても、あなたは変われます。
あなたが変われば、周囲とのズレも自然と減っていきます。
ぜひ、明日から試してみてください。
「聞き方の質」が、あなたの仕事の成果を確実に変えてくれます。