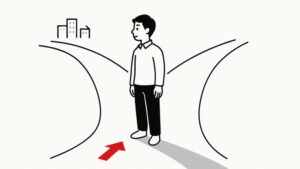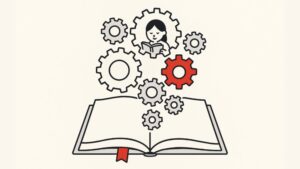辞めないキャリア戦略|“市場価値の見える化”で不安が消える理由

朝、コーヒーの香りがまだ立ちのぼるデスクで、ぼんやりとパソコンの画面を見つめていました。
前夜に届いた評価メールを開いても、胸の奥のもやもやは消えません。
「自分って、この職場でどれくらい必要とされているんだろう」——そんな問いが、頭の中で何度もリピートしていました。
正直、私はずっと“社内の物差し”だけで自分を測っていたと思います。
上司の一言で気持ちが揺れ、評価面談の結果で一喜一憂。
頑張っても報われない夜は、「転職する気はないけれど、このままでいいのかな」と天井を見つめたまま眠れなくなることもありました。
“悪くはない”日々ほど、静かに不安が積もっていく。
そんなある日、同僚が何気なく言いました。
「リクナビの診断、やってみた? 意外と面白いよ。」
怖かったんです。数字で突きつけられる“自分の現実”を見るのが。
でも、思い切って可視化してみたら、心が少し軽くなりました。
結果が良かったわけじゃありません。
「自分の強みはここ」「今の職場では活かしきれていない」と整理できたことで、初めて“次に何をすればいいか”が見えたんです。
これは、転職の話ではありません。
むしろ“辞めない前提”で市場価値を見える化することが、毎日の不安を静め、仕事の手応えを取り戻す近道でした。
本記事では、私の体験をもとに、
を紹介します。
最初は、“登録だけ・診断だけ”で構いません。
「何者でもない不安」を、言葉にできる安心に変える。
その一歩が、今の仕事を少し楽にしてくれます。
評価されない日々の中で揺らいだ「自分の価値って何だろう」
「それなりに頑張っているのに、評価が動かない。」
そんな感覚に、じわじわと疲れていませんか?
私もずっとそうでした。数字は悪くない。むしろ人より多くの仕事を引き受けていたのに、結果は「横ばい評価」。
努力と結果が噛み合わないあの違和感は、思っている以上に心を削ります。
けれど後になって気づいたんです。
私が感じていた苦しさの正体は、“頑張りが足りない”からではなく、「自分の価値を、会社の物差しだけで測っていた」からでした。
この章では、そんな気づきから始まった“市場価値の見つめ直し”の体験をお話しします。
評価面談のたびに感じた「理由のわからない疲れ」
評価面談の帰り道、私はいつも理由の分からない疲れに包まれていました。
数字は達成した。後輩のサポートも、引き継ぎもきちんと終わらせた。
それでも評価は「横ばい」。
会議室のドアが閉まった瞬間、心の奥で「なぜ?」が鳴り続ける。
上司の言葉ひとつで浮かれたり沈んだりする自分に、どこかで違和感を覚えながらも、
“社内の基準こそが、自分の価値”だと思い込んでいた。
だから、評価が上がらない=自分の実力が足りない——と。
でも、それはただの「社内物差し」でしかなかったと、今では思います。
社内評価と市場価値は、まったく別のものだと気づいた瞬間
あとで知ったのは、市場価値は“人気投票”ではないということ。
上司に好かれるとか、部署内で目立つとか、そういう話ではありません。
本来の市場価値とは、
「どんな課題を、どんな環境で、どのくらいの再現性で解けるか」を示す指標。
言い換えれば、“外の世界で必要とされる力”がどれだけあるか、です。
この視点を持てるだけで、「評価されない=価値がない」という思い込みが少しずつほどけていきました。
社内での立ち位置が変わらなくても、自分の見方を変えるだけで呼吸がしやすくなる。
「自分が解いてきた課題」を書き出すと、意外な強みが見えてくる
私はノートを開き、これまでに“解いてきた課題”を思い出せる限り書き出してみました。
売上アップ、顧客対応、部門間調整、トラブル収束——。
肩書きではなく、「どんな状況で」「何を」「どうやって」「どれだけ」やったかを時系列で整理する。
すると、当たり前すぎて誰も言葉にしてくれなかった強みが浮かび上がりました。
「火消しが得意」「初動が速い」「巻き込みがうまい」——どれも私らしい“クセ”であり、“武器”でもあった。
その瞬間、私は気づきました。
社内評価が動かなくても、自分の市場価値を整えることはできる。
むしろ“社内が変わらないうちに、自分を見える化しておく”ことが、一番の備えかもしれません。
- 社内評価と市場価値は別軸。
- 市場価値は「課題の再現性 × 希少性 × 需要」で測る。
- まずは「自分が解いてきた課題」を書き出すだけでも、自己評価が整い始める。
「評価されるため」ではなく「自分で選ぶため」に働く──
→ 市場価値を知って変わった働き方の軸と、揺らがない自分のつくり方 を、実体験を交えてまとめています。
「市場価値を知るのが怖い」——でも、知ることでしか得られない安心がある
正直、私はずっと“結果を見るのが怖い派”でした。
低く出たらどうしよう、自信をなくしたらどうしよう。
そんな気持ちが先に立って、何度も「あとでやろう」とタブを閉じました。
でも、怖さの正体は“現実”そのものではなく、「知らないこと」への不安だったんです。
知ることは怖い。けれど、知らないままのほうが、じわじわと心を削る。
私が実際に可視化してみて感じたのは、数字が自信を奪うのではなく、不安を“言葉にできる形”へ変えてくれるということでした。
「知るのが怖い」の正体は、“不確実性”という名の不安
心理学では、人は「分からない状態」が続くほど不安を感じやすいと言われます。
つまり、「今の自分の市場価値が分からない」は、心にとって最大級のストレス源。
私もまさにそうでした。
評価にモヤモヤしても、「自分が本当に低いのか」「たまたまそう見えるだけなのか」が分からない。
結果、何をすればいいのかも曖昧なまま、ただ焦りだけが積み上がっていく。
でも、“現状を見える化する”ことは、不安をコントロールする第一歩でした。
どんな数値でも、基準が見えれば「次にやるべきこと」に意識を向けられる。
私が怖さを越えられたのは、この感覚を体で理解した瞬間だったと思います。
「数値」は冷たくない。曖昧な不安を“課題”に変える道具
診断を受けた当初、結果のコメントを読む手が少し震えました。
けれど、意外なほど落ち着いて読めたんです。
なぜなら、曖昧だった不安が“課題”に変わったから。
「リーダーシップよりも調整力が高い」「粘り強いがスピード面に課題あり」——
こうしたフィードバックは、落ち込む材料ではなく、“改善の地図”でした。
ぼんやりした自信のなさが、「ここを伸ばせばいい」に置き換わる。
これだけで、翌日の仕事の集中力が少し戻ったのを覚えています。
怖さを和らげる3ステップ:診断 → 棚卸し → 相場確認
私が試したのは、診断(仮説)→棚卸し(根拠)→求人相場の確認(現実)という流れです。
- 診断で、自分の強み・傾向を仮説レベルで掴む。
- 棚卸しで、実際の成果や経験を照らし合わせて裏づける。
- 求人相場を見て、「どんな経験がいくらの価値で求められているか」を知る。
この順番にすると、心理的負担が最小限になります。
いきなり求人検索から入ると「自分なんて」と落ち込みがちですが、
まず“診断だけ”で仮説を立てると、「次に何を棚卸しすればいいか」が見えてきます。
- 不安の正体は不確実性。可視化で“対処可能な心配”に変わる。
- 診断→棚卸し→相場確認の順で、心理負担を最小化。
- 「低く出たら怖い」ではなく、「次に何をすればいいかが分かる」のが本当の価値。
「市場価値を知るのが怖いと感じた理由と、それでも知ってよかったと思えた瞬間」を、実体験を交えてまとめています。
→ 市場価値を知るのが怖い——それでも知ってよかったと思えた理由

リクナビNEXTで“自分の市場価値”を測ってみたリアル体験
「診断ツールって、結局は転職前提なんでしょ?」——正直、私もそう思っていました。
だから最初は、登録ボタンを押す指が止まりました。
けれど調べてみると、リクナビNEXTの診断は“登録だけでもOK”で、匿名設定や職場ブロック機能も完備。
これなら、「いざとなったら動ける準備」として試せるかもしれない——そう思い、軽い気持ちで始めたのがきっかけでした。
結果、驚くほど“怖くなかった”。
むしろ、数字とコメントが「今の自分をどう使えばいいか」のヒントになったんです。
この章では、私が実際にリクナビNEXTで市場価値を可視化してみた体験をリアルにお伝えします。
Step1:キャリアタイプ診断——「自分らしさの軸」が見える
最初に試したのは、リクナビNEXTの「キャリアタイプ診断」。
設問は多いものの、テンポよく答えられ、10分ほどで結果が表示されました。
印象的だったのは、結果が「良い・悪い」で分かれるのではなく、“自分の働き方の傾向を可視化する”という点。
たとえば私の場合、診断では「協調型×挑戦バランス型」という結果。
これが、自分でもうすうす感じていた“慎重だけど責任感が強い”部分と重なっていて、少し安心したのを覚えています。
「強み」だけでなく、「他者比較で弱みになりやすい点」も表示されるため、
「伸ばす」と「工夫で補う」の線引きがしやすいのもメリットでした。
Step2:年収相場の確認——数字が「焦り」を「整理」に変える
次に確認したのは、「年収相場」の項目です。
職種・経験・勤務地を入力するだけで、同条件の人の“年収レンジ”が出てきます。
このとき意識したのは、“平均値”ではなく“幅”を見ること。
たとえば「500〜700万円」と出たら、
「上限との差=今後の伸びしろ」「下限との差=安心ゾーン」として捉える。
そうすると、年収という数字に一喜一憂せずに済むようになりました。
「現状維持でも焦らなくていい」「伸ばす方向性を決めればいい」と思えるだけで、気持ちがかなり軽くなります。
Step3:スカウト設定——“受け取るだけ”で市場のリアルを知る
診断後、プロフィールを最小限に整え、「スカウトを受け取るだけ」に設定しました。
これが、思った以上に収穫のある体験でした。
どんな企業・職種・条件から反応が来るのかを眺めているだけで、
「自分の経験が求められている業界」や「想定よりも年収が高い職種」など、
“実需ベースの現在地”がリアルに見えてきたんです。
転職活動というよりも、“外の世界から見た自分の強みチェック”。
それくらいの距離感で使うと、心の負担なく市場感覚を取り戻せます。
- まずは無料・匿名配慮ありの診断から。
- 「幅」で相場を見ると、数字に振り回されなくなる。
- スカウトを“受け取るだけ”でも、今の市場での立ち位置が分かる。
実際に私が受けた→リクナビNEXTのキャリアタイプ診断でわかった“自分でも気づかなかった強み”について、リアルな体験をまとめています。
診断結果で見えてきた“自分の強みと課題”
診断を受けたあと、私は思いました。
「数字より、“言葉”の方が刺さるな」と。
グラフや点数ももちろん参考になりますが、
結果に添えられたコメント——それが、
“自分では当たり前と思っていた行動”を強みとして見せてくれたんです。
他人との比較ではなく、“自分の中でどう再現できるか”に目を向けることで、
初めて「これが自分の武器なんだ」と実感できました。
この章では、診断をもとに私がどのように強みと課題を整理し、
それを“行動の設計図”に落とし込んだかをお話しします。
「ただの性格」だと思っていた特徴が、強みだった
診断で出てきた私のキーワードは、
「初動が速い」「関係構築」「合意形成」「火消し」。
どれも、日常の延長線上にあって、
自分では“性格”のように思っていた要素でした。
でも、改めて見返すと、これらはすべて
「職場の混乱を減らす」「人を動かす」「物事を前に進める」力。
つまり、“再現性のある成果の起点”だったんです。
それに気づけただけでも、少し自信が戻りました。
評価は上司が決めるけれど、強みは自分で定義できる。
そう思えたのは、この診断が初めてでした。
「事実・再現性・工夫」で強みを言語化する
強みを“なんとなく”で終わらせないために、
私はノートに3つの項目を設けました。
- 事実に紐づけて言語化する
例:どの部署で、どの規模のプロジェクトを、どの期間で動かしたか。 - 再現性の証拠を集める
例:トラブル対応を仕組み化したり、引き継ぎテンプレートを残す。 - 弱みの“工夫”を設計する
例:資料作成が苦手なら、テンプレートを作る・レビュー頻度を固定する。
この3点セットを回すことで、
「頑張りました」ではなく、「こういう条件で、こう動いて、こう成果を出した」と
語れるようになりました。
言葉が変わると、任される仕事の質も変わる
この整理を続けていくうちに、社内での会話も変わっていきました。
評価の場でも、漠然とした努力報告ではなく、
「〇〇の状況で△△を行い、□□の結果を出しました」と具体的に伝える。
すると、不思議と相手の反応が違うんです。
評価の点数がすぐ上がるわけではなくても、
「この案件、任せてみようか」と言われる機会が増えました。
見える化は“上司にアピールするため”ではなく、
“任される仕事の質を変えるため”のツールだと気づきました。
- 強みは“性格”から“資産”に変換して初めて価値になる。
- 「事実・再現性・工夫」の3点セットで言語化する。
- 可視化は評価を上げるためではなく、任される仕事を変えるために効く。
数字だけでは見えない“自分の価値”に気づけた実体験を、
→ 年収診断で見落としていた強みと、納得できる自分の答え にまとめています。
まとめ|“市場価値を知る”ことは、自分を信じる根拠を持つこと
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
もし少しでも「自分の価値を確かめたい」と思ったなら、それは立派な一歩です。
市場価値を知ることは、転職の準備ではなく、「自分を信じる根拠」を取り戻す行為だと私は思います。
私自身、何かが劇的に変わったわけではありません。
でも、「いざとなれば動ける」「今の自分を言葉で説明できる」——この2つを持てただけで、
毎日のモヤモヤが少しずつ静かになっていきました。
- 社内評価と市場価値は別軸。
市場価値は、外の課題を解く“再現性”で測る。 - 不安の正体は不確実性。
診断→棚卸し→相場確認の順で、心は落ち着く。 - 強みは「言語化→証拠化→再現化」で“資産”になる。
評価よりも、任される仕事が変わる。
小さく見える化するだけで、心は確実に軽くなります。
「今の自分」を知ることは、攻めるためだけでなく、安心して働き続けるための防具にもなります。
私が最初に踏み出したのは、
「診断を受ける」→「スカウトを受け取る」のたった2ステップでした。
最初は“登録だけ”のつもりでしたが、それだけでも仕事の見え方が変わりました。
職務経歴書まで登録しておくと、あなたの経験に関心を持つ企業からスカウトが届きます。
いま転職する気がなくても、“自分の棚卸し”としておすすめです。
これまでの経験を言葉にするだけで、「自分の価値」を静かに再確認できる。
“準備だけ”でも、後の安心感が違います。
| 分類 | 出典名 | 概要 | URL |
|---|---|---|---|
| 労働市場・キャリア動向 | 厚生労働省「令和6年版 労働経済白書」 | 労働市場の構造変化や転職行動の傾向を分析。30〜40代ミドル層の転職動向や人材流動性の推移を確認できる。 | https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/index.html |
| 労働意識調査 | リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2024」 | 働く人の転職意欲、キャリア意識、年齢別の市場価値認識に関するデータを掲載。 | https://www.works-i.com/surveys/panel/ |
| 転職行動統計 | Indeed Japan「転職動向レポート2024」 | 日本国内における転職意欲層・非転職層の割合、求職活動の傾向をまとめた年次レポート。 | https://jp.indeed.com/lead/research |
| 診断ツール(公式情報) | リクナビNEXT「グッドポイント診断」 | 18種類の強みから5つを抽出し、自己理解を支援する公式診断ツール。登録後無料で利用可能。 | https://next.rikunabi.com/goodpoint/ |
| 診断ツール(公式情報) | doda「年収査定・キャリアタイプ診断」 | ビッグデータを活用し、職種・経験・地域別の適正年収とキャリア傾向を算出する公式ツール。 | https://doda.jp/diagnosis/ |
| 心理学・行動科学 | 日本心理学会「心理学辞典:不確実性と不安」 | 「不確実性が不安を増幅する」心理的メカニズムに関する学術的説明。 | https://psych.or.jp/publication/psych_dic/ |
| キャリア理論 | ダグラス・ホール『プロティアン・キャリア論』 | 「自律的キャリア形成」「市場価値=再現性と適応力」という考え方を提示した代表的理論書。 | (参考書籍)ISBN: 978-4788513517 |
| 人材評価ロジック | 経済産業省「未来人材ビジョン(2022)」 | 企業が求めるスキル・行動特性、リスキリングの方向性をまとめた資料。市場価値の定義に関する国の見解。 | https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/vision.html |
| キャリア支援・専門家の見解 | パーソルキャリア公式コラム「市場価値を高めるとはどういうことか」 | キャリアアドバイザー視点での市場価値の捉え方、再現性と希少性の考え方を紹介。 | https://www.persol-career.co.jp/hatalabo/hr-column/ |