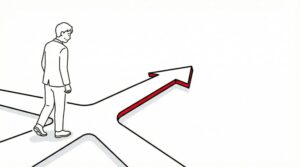リクナビNEXTのキャリアタイプ診断でわかった|自分でも気づかなかった“強み”と向き合う時間

夜、ソファに沈み込みながら、なんとなくスマホを開く。転職する気はないのに、求人サイトのタブだけが増えていく——以前の私は、そんな夜をいくつも過ごしていました。
「キャリアタイプ診断って、本当に意味あるの?」
半信半疑のまま試してみたら、結果画面を見た瞬間に思わず笑ってしまいました。“意外と当たってる……”。そして、そこに書かれていた“私の仕事スタイル”が妙に腹落ちして、翌日からのコミュニケーションが少しだけ変わったんです。
この記事では、私が実際に受けた体験をもとに、
を等身大で共有します。
“診断=自己理解の入り口”。たった5分のチェックが、思っていた以上に心の整理を助けてくれました。
「まずは自分を知る」ことから、次の選択肢は静かに動き出します。
「転職する気はないけど…」そんな“なんとなく”から始まった自己理解
「何かを変えたい」と思っていたわけじゃない。
けれど、日々の小さなモヤモヤが、いつのまにか胸の奥に積もっていく。
私がキャリアタイプ診断を受けたのは、そんな“曖昧な違和感”が静かに限界を迎えそうな頃でした。
行動の理由なんて、最初はほんの思いつき。
でも振り返れば、その“なんとなく”が、自分を見つめ直す最初のきっかけになっていました。
転職する気はなかったけど、モヤモヤしていた
正直、転職するつもりはありませんでした。
評価が極端に悪いわけでもないし、致命的な不満があるわけでもない。
ただ、会議が終わるたびに、胸の奥に説明しづらいモヤモヤが残る。
頑張っているのに空回りしている感覚。
上司とのすれ違いも、「言い方」なのか「価値観の違い」なのか、自分でも切り分けができない——そんな日々でした。
“このままでも困らない”けれど、“何も変わらない”ことへの不安が、少しずつ積もっていった。
そんなとき、友人との雑談で「タイプ診断って、当たるときはズバッと来るよね」と言われ、帰り道にふとリクナビNEXTを開きました。
“登録だけなら”と、とりあえず触ってみたのが始まりです。
軽い気持ちで受けた“自己理解の実験”が、意外と深かった
最初はほんの興味本位でした。
占いの延長くらいの感覚で、「どうせ大したことは出ないだろう」と思いながら質問に答えていきました。
ところが、回答しているうちに「自分はどんなときに動きやすいか」を考える時間になっていたんです。
つまり、診断を受ける行為そのものが“自分を振り返るワーク”になっていた。
たった数分の設問でも、思考の整理効果は想像以上でした。
“大丈夫”なうちに、自分を言語化しておくのがいちばん楽だ。
後になって焦らないための“5分の棚卸し”だと思えば、気がラクになります。
- 転職前提の悩みではなくても、日々に“言語化しづらい違和感”はある
- その違和感の正体は、「価値観のズレ」かもしれない
- 迷ったときは、“軽い自己理解の実験”から始めてみる
たった15分で“自分の取扱説明書”ができた感覚
正直、診断を受ける前は「どうせ当たり障りのない結果が出るんだろう」と思っていました。
けれど、表示された一行目を読んだ瞬間、思わず笑ってしまったんです。“これ、完全に私じゃないか”と。
曖昧だった自分の“働き方のクセ”が言葉になった途端、これまで感じていたモヤモヤが少しずつ整理されていきました。
たった数分の診断でも、“見えなかった自分”に出会うきっかけになる。そんな感覚でした。
自分らしさ”を言葉で見せられて、思わず納得
結果画面の最初に表示されたのは、“仕事で何を大事にしているか”という私の価値観でした。
そこには「成果やスピードより、再現性と信頼性を重視」「まず全体像を握ってから動く傾向」といった言葉が並び、“そう、まさにそれ”と内心うなずいていました。
普段はうまく説明できない自分の判断基準が、短いフレーズで整理されているだけで、心のざわつきが静かになる感覚がありました。
さらに、過去の行動傾向に触れた項目では、「まずは一人で仮説を立て、確かめてから共有する」というスタイルが指摘され、まさに私の“癖”そのもの。
ここでようやく、「会議で即興的に意見を出す」タイプの上司とズレる理由が腑に落ちました。
私が遅いのではなく、“準備してから話したい性格”だっただけ。
ラベルが付いた途端、自己否定がすっと薄れました。
“得意・不得意”のバランスが見えると、無理しなくてよくなった
もう一つ、響いたのは“得意・不得意のバランス”です。
私は新規開拓の0→1より、既存の仕組みの1→10に向いている。
反対に、未完成のものを人前で動かしながら調整するのは苦手。
これを認めた瞬間、「苦手を根性でねじ伏せる」のをやめられました。
代わりに、0→1が得意な同僚の初動に早めに乗り、私は構造化と運用に専念する。
チーム全体のスピードが上がり、私自身のストレスも減りました。
“得意に集中する勇気”が、結果的にチームを強くする。
そう気づけただけでも、診断を受けた価値がありました。
- 診断は“自分の言葉にしづらい基準”を短いフレーズで示してくれる
- ズレは「能力の優劣」ではなく「スタイルの違い」で起きると分かる
- 得意/不得意を認めると、チーム設計と役割分担が楽になる
診断結果を“現場の自分”に落とし込むと、仕事が少しラクになった
診断を受けて終わりではなく、“そこからどう使うか”が本当のスタートでした。
結果を見て納得しただけでは、日常は変わらない。
けれど、少し視点を変えるだけで、上司との会話や仕事の選び方が驚くほどスムーズになりました。
“自分を理解する”ことは、“相手との接点を設計し直すこと”でもある。
私が実際に試して効果を感じた工夫を、ここで2つ紹介します。
上司との“ズレ”は性格ではなく、タイプの違いだった
診断後、私は上司との打ち合わせ前に「仮説メモ」を作るようにしました。
1枚で、目的・前提・選択肢・懸念を整理。
これがあるだけで、即興重視の上司とも“地図を共有してから走る”感覚になり、議論が噛み合うように。
上司のスピード感に乗りつつ、私の慎重さも活かせる落とし所が見えてきました。
また、会議の場でまっさらな案を求められたときは、「まず3つの方向性だけ出します。詳細は明日までに案を固めます」と宣言するようにしました。
自分のスタイルを言語化して伝えるだけで、“遅い人”ではなく“段取りが丁寧な人”として受け止められるようになりました。
“理解してもらう努力”ではなく、“伝わる設計”に変える。
それだけで、上司との摩擦は静かに減っていきました。
“自分の軸”を意識して選ぶと、迷いが減った
案件の打診が来たときも、“自分の軸”で見極めます。
たとえば「短納期で仕様が流動的」という条件は、私のストレス源になりやすい。
一方で「既存業務の改善・標準化」や「検証・ドキュメント整備」は、私の強みと好みが重なる領域。
“やらない”のではなく、“向いている形に変えて貢献する”という発想ができるようになりました。
これだけで、仕事に対する罪悪感や焦りがぐっと減りました。
得意な形で貢献することは、わがままではなく戦略。
診断がその判断基準をくれたのだと思います。
- 事前に“地図”を用意して会話すると、すれ違いが減る
- 自分のスタイルを先に宣言すると、評価の座標軸が変わる
- 案件選びは「嫌い避け」ではなく「強み活用」に寄せる
まとめ|“キャリアの答え”は出なくても、方向が見えた
ここまで振り返って感じたのは、「自分を知ること」は、転職の準備というより“日々を軽くする習慣”だということです。
結果がどうであれ、「自分の軸」を言葉にできるだけで、仕事や人間関係のノイズが少しずつ減っていく。
怖いと思っていた“診断”が、思いがけず優しい鏡になりました。
やってみることでしか見えない“自分の輪郭”がある
診断は答えではなく、対話のきっかけでした。
短いフレーズで自分の基準を示されただけで、日々の選択やコミュニケーションの質がじわっと変わります。
小さな違和感の正体に名前が付くと、「自分の扱い方」が分かるからです。
“正解を探す”より、“自分を理解する”ほうが前に進める。
その実感をくれたのが、このキャリアタイプ診断でした。
無料の「キャリアタイプ診断」で、“自分らしさ”を再確認してみよう
転職する気がなくても大丈夫。
むしろ、転職しない人ほど“自分の使い方”を知っておくと、仕事が楽になります。
5分でできるので、「今日は自分の地図を一枚、増やす」くらいの気軽さで試してみてください。
- 診断は「ラベル付け」ではなく「自己理解の入り口」
- スタイルの違いが分かると、関係が楽になり、成果も安定する
- 5分の自己理解が、明日の小さな選択を確かに変える
会員登録は5分で完了します。
「キャリアタイプ診断」は転職する気がなくてもOK。
今の自分を客観的に見つめる“きっかけ”として試してみてください。
職務経歴書まで登録しておくと、あなたの経験に関心を持つ企業からスカウトが届きます。
いま転職する気がなくても、“自分の棚卸し”としておすすめです。
これまでの経験を言葉にするだけで、「自分の価値」を静かに再確認できる。
“準備だけ”でも、後の安心感が違います。
「自分のタイプ」を知ったら、次は“自分の価値”を見える化するステップへ。
不安を整理して前向きに働くためのヒントをまとめました。
→ キャリアの不安を解消する「市場価値の見える化」実践ガイド

「市場価値を知る」といっても、その向き合い方は人それぞれ。
他の記事では、“知る勇気”や“見える化のコツ”、“行動後の変化”なども紹介しています。
気になるテーマから、自分のケースに重ねて読んでみてください。